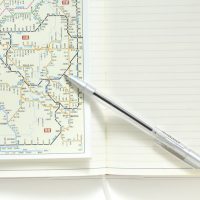社用車管理の法的要件と実務のポイント|運用からコスト管理まで
社用車管理は、法的義務であり、事故リスクの低減やコスト削減にも直結する重要な業務です。特に近年は、デジタル化による管理手法の変化や、働き方改革に伴う労務管理の厳格化など、従来とは異なる新しい課題も生まれています。本記事では、企業が実施すべき社用車管理の法的要件から具体的な管理方法、さらには業務効率化のポイントまで解説します。
目次
社用車管理の基本と法的責任
社用車は企業の重要な資産であると同時に、事故が発生した場合には重大な責任を伴います。適切な管理体制を整備することは、企業の安全配慮義務を果たすうえでも欠かせません。
社用車管理の目的と重要性
企業における社用車管理の主な目的は以下の3点です。
- 従業員の安全確保
- 車両の資産価値の保全
- 経費の適正化
これらを実現するためには、運転者の健康チェックやドライブレコーダーによる運転状態の把握、定期点検や車両状態の記録、燃費記録や修繕履歴、効率的な配車計画などの異なるデータを包括的に扱う必要があり、それぞれに適したデータ収集と連携体制の構築が求められます。
企業に求められる法的義務
企業は以下の法律に従って社用車を管理することが義務化されています。
道路運送車両法
事業用自動車の使用者は日常点検と定期点検を実施する義務があります。
- 1年ごとの定期点検整備(車検)
- 3ヶ月ごとの定期点検
- 運行前の日常点検
日常点検では、ブレーキ、タイヤ、ライトなどの基本的な項目を確認し、記録を保管する必要があります。
罰則: 事業用車両(バス・トラック・タクシーなど)の場合、法定点検の未実施に対し、30万円以下の罰金が課される可能性があります。日常点検整備の未実施に対する直接的な罰則はありませんが、点検不備による事故の場合は罰金や違反点数が課される可能性があります。
出典:道路運送車両法 | e-Gov 法令検索
道路交通法
一定台数以上の自動車を使用する事業所には安全運転管理者の選任が必要です。
- 乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用する場合
- その他の自動車を5台以上使用する場合
該当する場合、選任後15日以内に警察署長に届け出る必要があります。
罰則: 道路交通法第74条の3に基づき、安全運転管理者を選任しない場合、企業には罰則が科されることがあります。
出典:道路交通法 | e-Gov 法令検索
これらの法令違反は罰則だけでなく、事故発生時の企業責任の増大や社会的信用の失墜にもつながる可能性があるため、適切な車両管理が重要です。
社用車管理の具体的な内容と目的
社用車管理の実務は、日々の運行管理から定期的な点検整備まで、多岐にわたります。それぞれの業務がどのように管理目的の達成に貢献するかを解説します。
運転日報による運行管理
運転日報は、車両の使用状況を把握し、適切な管理を行うための基本となる記録です。日報には、使用者名、使用時間、走行距離、使用目的などの基本情報を記録します。
特に重要なのは、走行距離と燃料補給量の記録です。これらのデータは、燃費の把握や不正使用の防止に役立ちます。また、車両の状態に関する気づきを記録する欄を設けることで、早期の不具合発見、コスト管理にもつながります。
点検・整備による安全性と資産価値の維持
車両の点検・整備は、安全運行の基本であり、資産価値の保全にも不可欠です。日常点検では、タイヤの空気圧やオイル量、ランプ類の点灯確認など、基本的な項目を確認します。定期点検は、法定で定められた期間ごとに、整備士による専門的な点検を実施します。
これらの点検・整備により、重大な故障や事故を未然に防ぎ、車両の長期的な価値を維持することができます。また法令遵守の面からも、定期的な点検記録の保管は企業にとって重要な意味を持ちます。
経費管理によるコスト最適化
社用車の経費管理は企業の収益性に直接影響します。主な管理対象は以下の通りです。
- 燃料費:最も大きな変動費であり、適切な管理による経費削減が可能
- 修繕費:計画的な整備による突発的な高額修理の回避
- 保険料:適切な保険プランの選択と定期的な見直し
- 車両の減価償却費:最適な更新計画の策定
特に燃料費は変動費の大きな部分を占めるため、運転日報のデータと連携させた分析がコスト削減につながります。
運転者教育と労務管理による安全確保
運転者教育は、企業の安全配慮義務を果たすための重要な施策です。安全運転管理者(または車両管理の担当者)は以下の取り組みを行います。
- 定期的な安全運転研修の実施
- 交通法規の確認や事故事例の研究
- 運転者の健康状態の確認と適切な勤務時間管理
- 長時間運転が必要な場合の休憩時間確保の指導
これらの教育と労務管理は、事故リスクの低減だけでなく、企業の社会的責任の遂行にも寄与します。
事故予防と緊急時対応
事故予防には、運転者の意識向上と、客観的なデータに基づく対策の両方が必要です。ヒヤリハット情報の収集と分析、事故多発地点の把握などを通じて、効果的な予防策を講じます。
事故発生時の対応手順は、あらかじめマニュアル化しておくことが重要です。緊急連絡先リストの整備や、保険会社との連携体制の確立なども欠かせません。事故対応の迅速さは、二次被害の防止や損害の軽減に直結します。
管理業務の効率化とデジタル活用
近年は、テクノロジーの進歩により、社用車管理の効率化が進んでいます。適切なツールの選択と活用が、管理業務の質を高めるとともに、作業時間の短縮や人的ミスの削減による省力化を実現する鍵となります。
車両管理システムの活用方法
車両管理システムを導入する際は、自社の規模や業務内容に合った選択が重要です。
近年では、タクシー事業者向けなど、業界特有のニーズに特化したシステムも登場しています。例えば、車検管理や保険管理に特化したシステムでは、以下のような機能が実装されています。
- 車両登録や保険・車検の更新時期を事前にメール通知による期限切れリスクの防止
- 帳票のシステム出力による転記ミスの防止と業務効率化
- 車検証と同じ配置のデータ入力画面による使いやすさの向上と入力ミスの低減
- 複数営業所の車両を一元管理できる機能による管理の統一化と業務効率の向上
- 本拠地変更手続きのデジタル化による申請作業の簡素化と処理時間の短縮
特に重要なのは、システムが現場の業務フローに適合していることです。日常の運行管理や点検記録の実務に即した画面設計や、手作業での集計作業を自動化する機能など、具体的な業務課題を解決できるシステム選びが効率化の鍵を握ります。複雑すぎるシステムや必要以上の機能は、かえって業務の非効率を招く可能性があります。また、既存の社内システムとの連携可能性も検討のポイントとなります。
車両管理システムについては、車両管理とは?企業が知るべき重要性と業務内容・システムの選び方の記事もご覧ください。
管理業務の効率化のポイント
業務の効率化には、まず現状の課題を明確にすることが重要です。たとえば、書類作成に時間がかかっている、データの集計に手間がかかっているなど、具体的な問題点を洗い出します。
また、効率化を進める際は一度にすべてを変更するのではなく、優先順位をつけて段階的に実施することをお勧めします。段階的に実施することで現場の意見を取り入れながら、より現場の課題に即した改善策を検討しやすくなります。
コスト削減の具体的施策
コスト削減は、単なる経費の圧縮ではなく、適切な管理による無駄の排除を目指します。たとえば、走行ルートの最適化による燃料費の削減や、適切な点検整備による修繕費の抑制などが具体的な施策となります。
加えて、車両の使用頻度や走行距離のデータを分析することで、適正な車両数の見直しも可能になります。必要に応じてカーシェアリングの導入を検討するなど、柔軟な対応をすることも効果的です。
さらに、テレマティクスシステムを活用した急発進・急ブレーキの削減指導は、燃費向上と事故リスク低減の両面で効果を発揮します。保険料の見直しや、車両の計画的な更新による維持費の最適化も、長期的なコスト削減につながります。データに基づいた継続的な改善を行うことで、安全性を確保しながらコスト効率の高い車両運用が実現できるでしょう。
まとめ
社用車の適切な管理体制の構築は、安全確保と法令遵守の面から企業にとって避けて通れない重要な課題です。特に、法律で定められた安全運転管理者の選任や日常点検の実施などは確実な対応が求められます。また、運転日報による日々の運行管理や、定期的な点検整備の実施は、事故予防とコスト管理の両面で大きな効果をもたらします。
こうした社用車管理業務は多岐にわたり、手作業での対応には限界があります。近年では、車両管理システムの導入によって、これらの業務を効率的に進められるようになってきました。データに基づいた管理を行うことで、安全性の向上はもちろん、燃料費の適正化や車両の稼働率向上など、具体的な成果も期待できます。
重要なのは、自社の実情に合った管理体制とデジタルツールの組み合わせを段階的に構築していくことです。本記事で解説した基本的な管理方法を土台としながら、必要に応じてシステムを活用し、より効率的で安全な車両管理を実現していきましょう。
Will Smartでは、「移動を支えるテクノロジー企業」として、地域交通の維持や再編のためのデータ分析基盤の構築やモビリティ関連システムの開発を行っています。地域交通のリデザインや関連システムの構築にお悩みの方は、ぜひWill Smartのサービスページをご覧ください。
メールマガジンに登録しませんか?
本サイトを運営しております株式会社Will Smartは公共交通・物流・不動産などの社会インフラの領域においてIoT技術やモビリティテックを活用したGX×DXの取り組みに注力しております。
メールマガジンではWill Smartの最新の取り組み事例やミライコラボのコンテンツ情報をなどお届けします。下記の登録フォームよりぜひご登録ください。